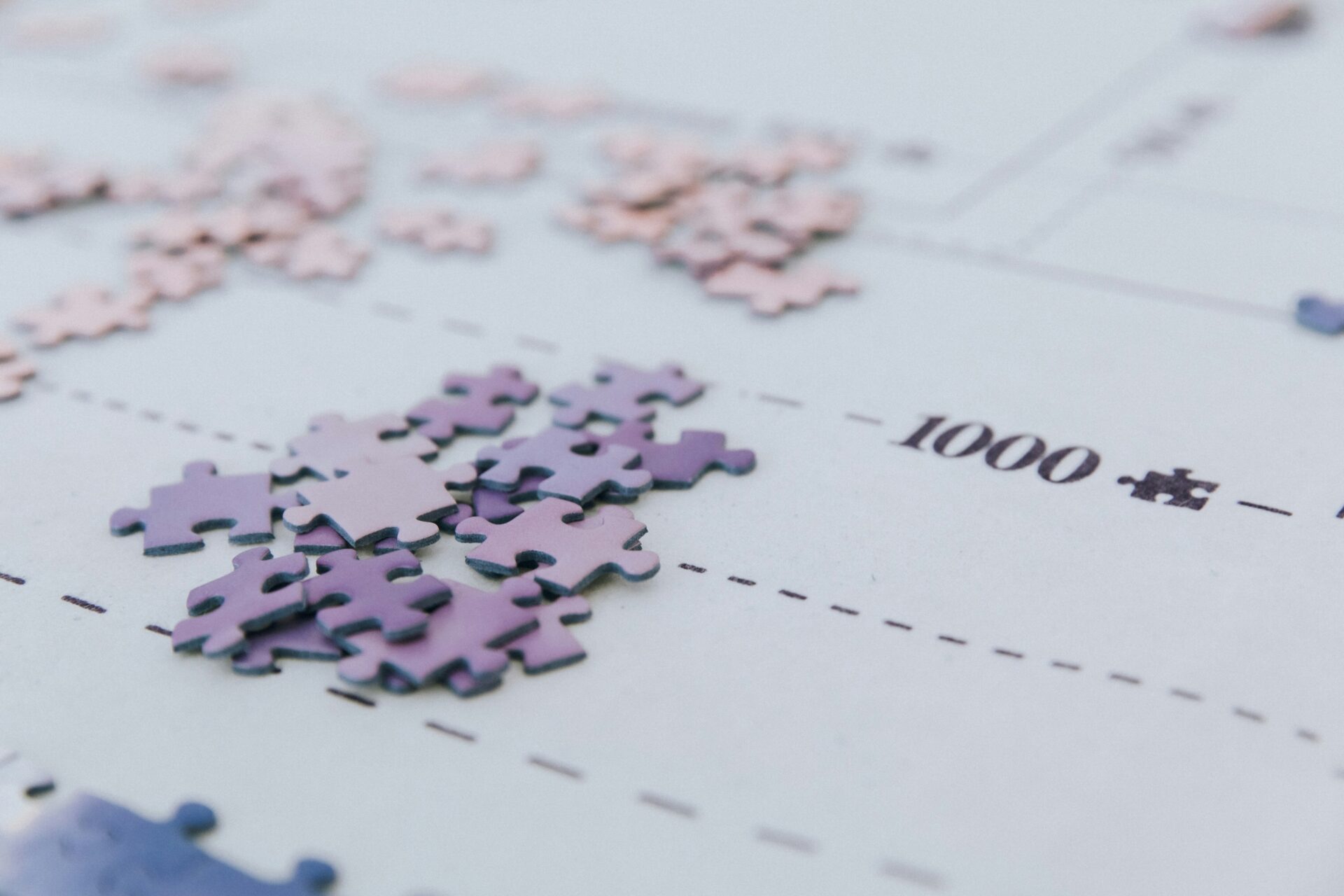タナトフォビア(死恐怖症)の改善法を考えてみる【書籍紹介も】

本記事ではあくまで素人の私が考えてみた、月並みな内容のタナトフォビア改善法を書いてみる。また、最近読んだタナトフォビアの本をちょっと紹介してみます。
タナトフォビアの改善法を考えてみた

安心、共同体感覚を得る
タナトフォビアの原因として”慢性的な孤独感”があるかもしれないと思っている。普段、周囲の人との温かい交流や共同体感覚を実感できれいれば、もしかしたらここまで「死」についてじっくり考えずに済むのかもしれない。
何のメンタル不調にも「安心を得ること」は大事だ。実際にすぐ取り組めそうなこととしては、タナトフォビア仲間との交流がある。
それから、もしタナトフォビアの原因と思しききっかけがあれば、カウンセリングで話したり、本格的なトラウマ治療してもいいと思う。
「死」の概念を身近なものにする
タナトフォビアだと「死」から目を逸らしたい気持ちになるけど、少しずつ向き合ってみるのは良さそう。
簡単なのはタナトフォビアを扱った本だと思う。最初から「死」を直球に書いたものは怖いかもしれないので、まずは「死って怖いよね」という内容に触れるのは良いんじゃないだろうか。
それから、もう少し進めば身近な人に親戚の死や、葬式の話とか聞いてみたりもできそうだ。医師のドキュメンタリーを観てみたり。病気の人の手記や、哲学書も良いと思う。
あとあまり現実的ではないが、勇気があれば直接「死」に携わる仕事をするという手段も考えられる。もっとソフトにするなら、老人ホームや動物保護のボランティアとかだろうか(一時的にその場の空気を感じたり、話を聞いたりする)。
「死」を身近にするための選択肢自体は意外と多いと思う。そもそも「死」って身近なはずのものだから。
宗教・スピリチュアル
これがうまくハマればかなり強いとは思っている。もちろん入信したら最強だが、入信には劣るとも、興味のある宗教やスピの文化に触れてみるのもアリなのではと感じる。
「死ぬのが怖いから入信する」は宗教のかなりの原点である。宗教には、死への恐怖を和らげたり、得体の知れない物事への畏怖を落ち着かせる役割がある。
ただ、神話とかってただでさえ「それほんとか?」となるストーリーなのに、歴史的に金や権力の道具として使われ、教義の改ざんやアナザーストーリーの制作などをかなりしてきちゃったもんで、本当に信じるのってなかなか難しいよね。それでも、なかなか強固なコミュニティへの所属はできる。
そもそもなぜ、死は怖いのか

生き物として困るから
身も蓋もない話だが、死んじゃうと生き物として困るから。一番避けたいことだから。
生物の生きる目的は、種の保存だ。ちなみにこれは「みんな子どもを産むべき」と言ってるんじゃないよ。人間もたまたま文明を築いただけの動物だから、本能で怖いものは怖い。種が途絶えることは避けたいから。
だからみんな基本的に死ぬことは怖いけど、個人的に”強烈に怖い”と思う何かがタナトフォビアの人には特別にあったことになる。精神的な困り事は「本能」「野生」「動物」をベースにすると意味がわかることがある。
死ぬことは確定してるから
これは人間特有のことだけど、人間は未来を想像して心配することができてしまう。でも、この世にあるいろんな心配の中でも「死」だけは絶対だ。100%起こる。他と違って、心配が外れるということがない。少なくとも今の科学では。
というかこの世の他のいろんな恐怖症も「死」に繋がっているはずなのだ。最終的に。高所や閉所はもちろん、ピエロやヘビが怖いのも、最悪の場合それに殺される可能性を感じるからだろうし、ちょっと変わった恐怖症も、突き詰めれば最後に「死」に繋がると思う。
ピエロを見ても死なないことが圧倒的だろうが、死はどういうマインドで過ごそうと必ず訪れてしまう。だから怖い。杞憂とかないもん。
タナトフォビアの本を読んでみた
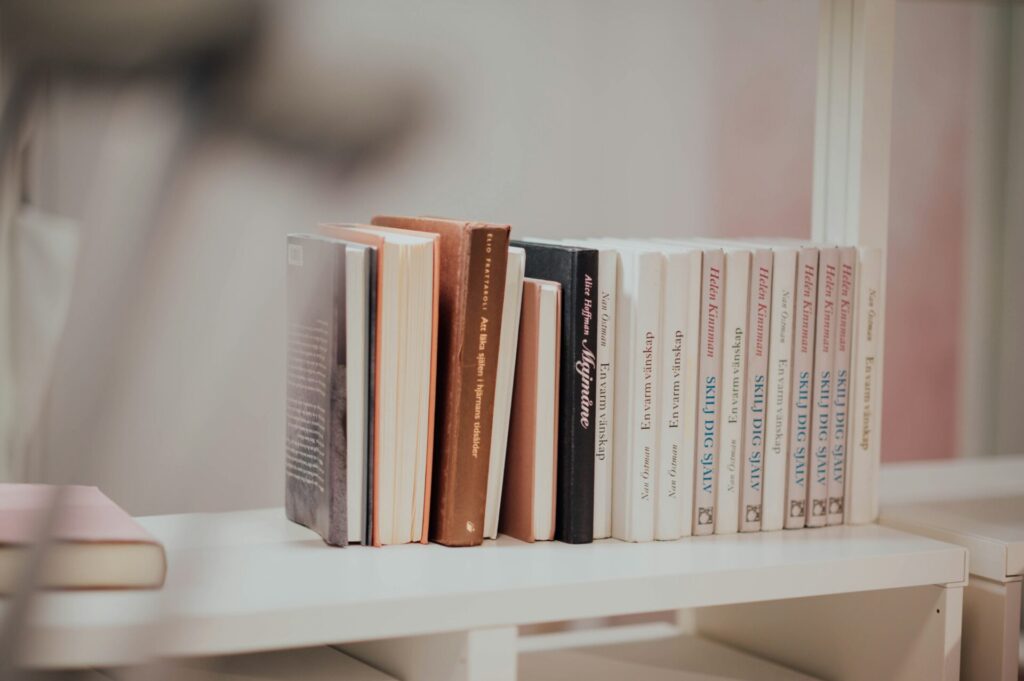
最近、Xの投稿にて『死ぬのが怖くてたまらない。だから、その正体が知りたかった。』(浦出美緒/SBクリエイティブ)という本を知ったので読んでみた。
タナトフォビアの著者が、医師、宗教社会学者、神経科学者、哲学者、小説家と「死」について対談した一冊である。専門的な話をしているのにとても読みやすく書かれている。
”意識がなくなるのが怖い”
作者の抱えるタナトフォビアの軸は「意識が消えてしまう恐怖」である。これは私も全く同じだ。もちろん死ぬときの痛みとかも怖いけど、それよりなにより「死んだらこの私の意識がプツッと消えてしまう」んだ。
私の場合はさらに、死んだあとの自分がいない街並みの様子や宇宙空間の行く末のことまで考えるし、毎日眠るのが怖い。寝ているあいだに何かの発作で死んだらどうしようとか、眠ったまま意識が消えちゃったら…と考える。
赤子が眠るのを嫌がるのは、睡眠が死に似ているからとか聞いたことがある。本当かは知らないが。単純に、眠い感覚が不快っていうのも聞いたことあるし。
一冊を通して、著者の言うことにはかなり共感した。その怖がり方に。
天国や輪廻転生に「都合がいい」と感じてしまうのも、一方で「それでも信じられるなら信じてみたい」と感じるのも。死後どうなるかについて正解が欲しかったりも。
タナトフォビアの根強さ
私が好感を持ったのが、これだけ有識者に話を聞いていても著者が持つ疑問や反発、まだまだ不安な心が正直に記されている点だ。
他の恐怖症に比べてもタナトフォビアは一筋縄ではいかない。どんな学術的観点から死を解説してもらったところでまだ怖いのは当たり前だ。
タナトフォビアの人の考えを知ることは慰めになり得ると思った。離人症もそうだけど、共感は救いになる。
ちなみに著者は「日本タナトフォビア協会」という協会を作り、そこで対話会も開催しているようだ。
私なりの結論:やはり宗教が強いのか
やっぱりこれだけ考えて、本を読んでみても、「死」や「死の恐怖」って結局どうしようもないんじゃないのかという切迫感が私にはある。
本の中には、意識をクラウド保存する技術研究の話なども出ていたが、私が通して読んだ感じ、「今のところ、やはり宗教が一強か?」という感じがした。専門家の皆さんもそれぞれ、宗教の話に触れていた。死を語るうえで当然のことだ。
死を避けることはできなくて、どうしても死ななきゃいけなくて、気を紛らわせるためにやはり宗教なのか。悪い言い方をすると、現実から目を逸らすために。私はスピリチュアルな旅に出るのか? そこを考えてみたい。
実際死ぬとき、私は何を思うのか

私は何よりも”突然死”を恐れている。プツッと終わるなんて、そんなのやだ。ただ、私の不摂生な生活ではありえることなのが怖いんですが…。
じゃあ、突然死を免れたとして、ゆっくり死ねたとして実際そのとき私は何を感じているか。おそらく現実的には”朦朧とした意識のなか、気づかないうちに死ぬ”だろう。なんと恐ろしい。そんなのやだ。でも、実際そういう人が多いだろう。
そして私に特徴的なのは、こう見えて希死念慮もあるってことだ。鬱だから。死にたいけど、死にたくない。これは両立するのだ。
死にたいっていうか、まぁ消えたいのが正確なんですけどね。どこかに消えてしまいたいという。でもね、「死にたい」って言葉が一番しっくりくるのだ…。
前から言っているように、私には「体の力を抜くと死んでしまうのでは」という強迫観念がある。リラックスできないと、私の患う離人症も治らない。
離人症の”症状自体”は哲学やスピリチュアルと絶対に混同してほしくないということは言ってきたが、治す方法は哲学やスピリチュアルでもいいと思っている。それについては、この記事↓でもちょっと書いています。

というわけで今回の記事は以上です。
私の患っている”離人症”とタナトフォビアの関係については以下の記事で考察してます。

今後も、タナトフォビアについて思うことがあればシリーズで書いていきたいと思います。