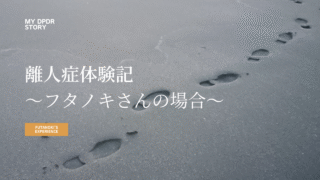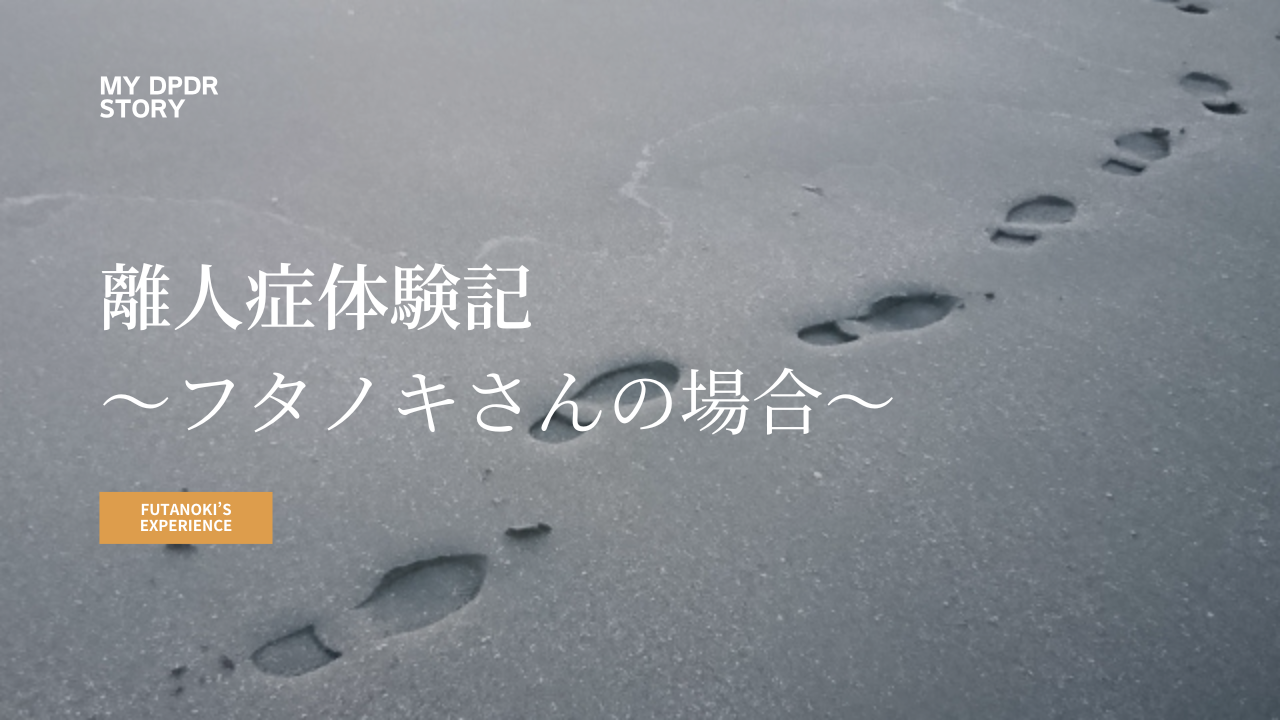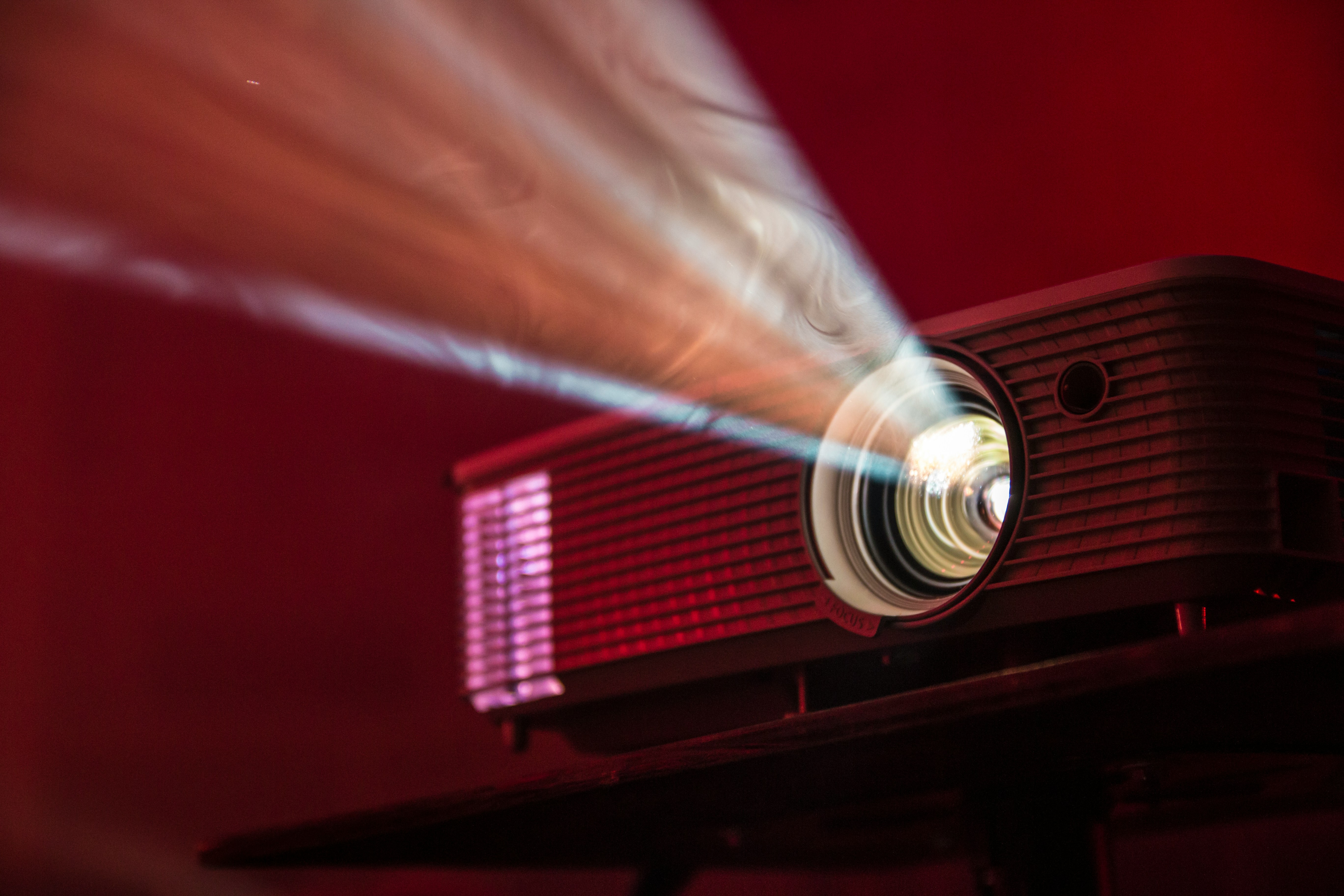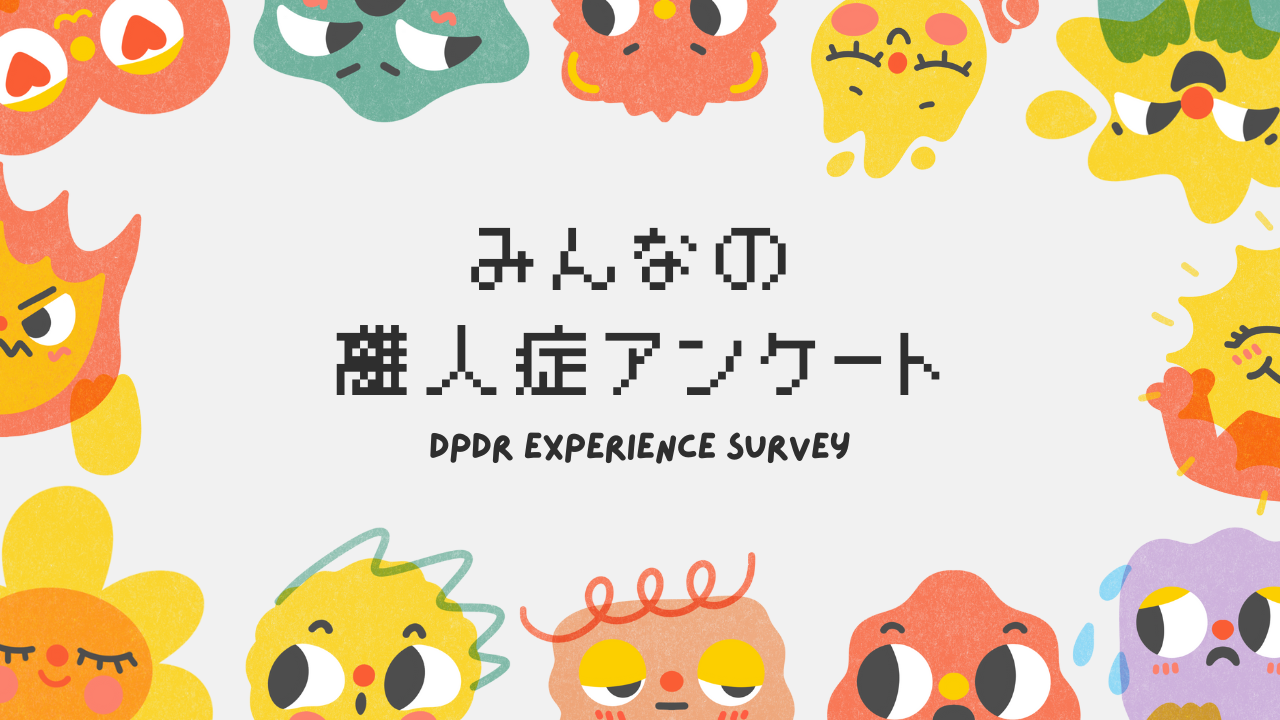私の離人症体験談~症状・治療歴、回復への考察~
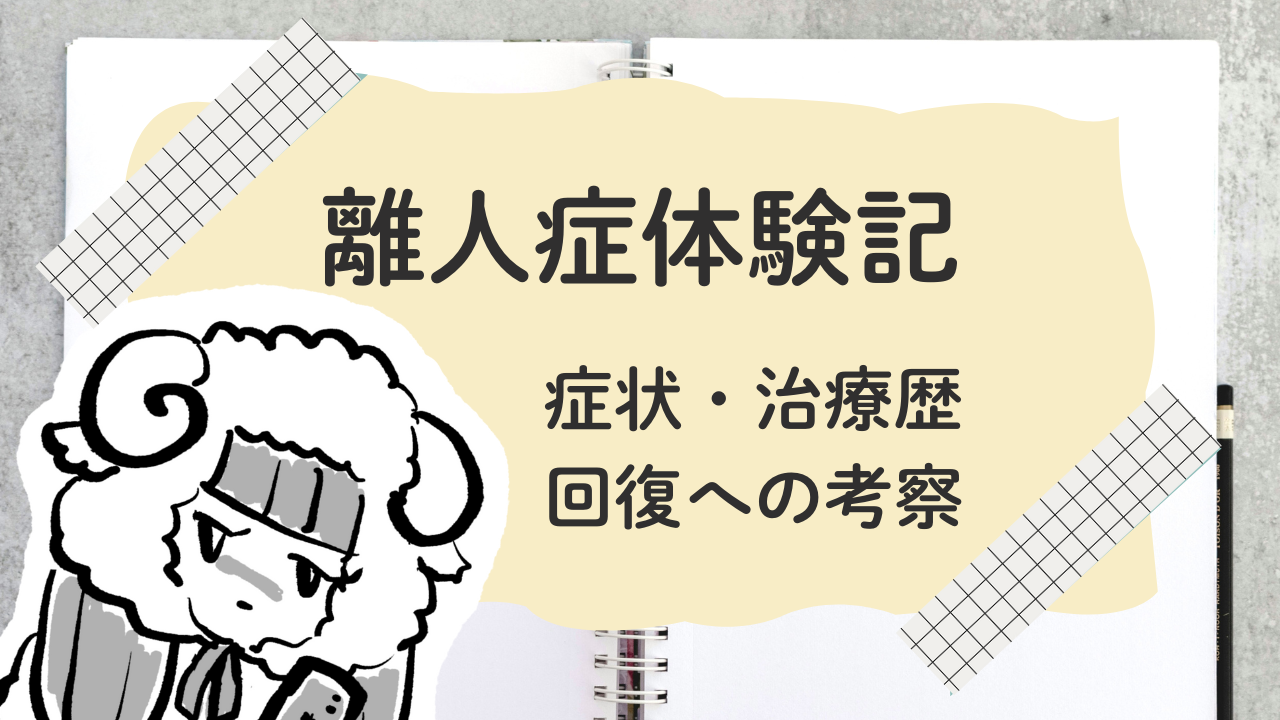
1. 概要
私は慢性的な離人症である。慢性的というのは24時間、ずっと離人感が出ていて現実に戻れていないということである。最初は単発で一過性の離人症だったのだが、気づいたらずっと現実に帰れなくなっていた。
この記事を書いている時点で、最初の発症から20年以上、慢性的になってからは15年以上である。
2. 発症時期・経緯
離人体験の最も古い記憶は中学校のときである。ある日、同級生とペラペラ喋っている自分を天井から見ていた。ここまでの幽体離脱視点はそれが最初で最後だったが、それ以降たびたび謎のふらつき・めまいのようなものに襲われるようになった。
それは体が疲れたときか、インターネットをした後によく現れた。発症当時は、家庭不和と、学校でのイジメ、および孤立(コミュニケーション下手)でストレスに苛まれていた。
その謎のふらつきがメンタル系の症状だとは大学生まで気づけなかった。時を同じくして、離人感は慢性的になっていった。
3. 主な症状
現実感の喪失
世界に膜がかかっていて、現実が現実のことだと思えない。スクリーンを見ているようだ。日常のあらゆることに実感がない。ひとつ言えることは、これは哲学的な話ではないし、中二病でもない。
物事に没入や熱狂ということがあまりできなくなり、とてもショックだ。これはクールで冷めてるとかじゃない。現実感がなくなると、自分にも周りの物事にも、息吹や生命力、魅力や輝きというものを感じられなくなるのだ。
自己感覚の変化
「私は誰?」という漫画みたいなことを感じる。けっこうゾッとする。他人の体に生きてるみたいだ。漫画みたいにかっこいいもんじゃない。実際はけっこう焦る。
そして感情がストレートに出てこない。感情がないわけじゃない。嬉しいこともイライラすることもある。でもそれに伴う「実感」がかなりバグっていて、他人の感情みたいで、気味が悪く、もどかしい。結果、感情の2割くらいが外に出て、残りの8割は体内で違和感の廃棄物として蓄積する。
よく「感覚鈍麻」や「失感情症(アレキシサイミア)」という言葉とごっちゃにされるが、実は全然意味が違う。感覚鈍麻みたいに温度やケガの痛みに気づきにくいのとは違うし、失感情症みたいに自分の感情自体に気づきにくいのとはまた別の話。
身体感覚の異常
自分がここに立っている感じがしない。自分の腕を触ってもマネキンのようだ。自分の声が他人のように聞こえて気持ち悪い。これも哲学が実存が…とかって話じゃなくてなんか物理的に、身体感覚的にそう感じるってことなのだ。五感に違和感があって、気味が悪い。
視覚はのっぺり平面で奥行がない。音楽はただの”音”に聞こえて情緒がない。においも人の鼻で嗅ぎ取っているようだ。
意識はボーっとして、グラグラ・フラフラしている。離人症は解離性障害(or解離症)というカテゴリの中に入っているが、解離の人に共通するのがこのボーッとした感じなんだと思ってる。
時間感覚のゆがみ
昔の自分と今の自分が繋がっている感じが乏しい。アイデンティティとは自己の連続性だという話をよく聞くが、それが断絶されている感じだろう。あと個人的に、解離してると時間が恐ろしく速く過ぎていく。
これらの症状は単に歳を取ったからじゃない。離人症の話をすると「歳を取ったら物事への感動も薄くなるし、昔のことも忘れるし、時間も速く感じるよ~」なんて言われたりするが、私は大学生のころから、世界から急激に鮮やかさが消えたままなのだ。
私の心身に、加齢による影響がないとは言わない。めっちゃある。ただ、離人症においては加齢で片付く話じゃなさすぎるのだ。
4. 発症の背景・要因
私の離人症発症の要因は以下のものだと思っている。
- 家庭環境(家庭不和、父親との関係など)
- 発達特性(ASD, ADHD)
- 学校生活(いじめ・コミュニケーションの困難による孤立)
- それらによる長期的な過緊張状態
遺伝や体質の影響ついては、よく知らない。
以上の要因で複雑性PTSDと鬱にもなってしまった。解離でボーッとしていて元気はないのに、体はいつも緊張で過覚醒状態であり、グッタリとソワソワとドキドキが同居している、なんとも込み入った状況である。
自己注目と反芻思考が大きな要因?
私は自己注視と反芻思考が止まらない。自己注目は言葉通り自分に注意を払いすぎてることで、反芻思考は嫌な考えがぐるぐる止まないことだ。これらがあると「今ここ」という現実にとどまることができない。
離人症というと、イメージだけで「今ここを意識してみてください」と言われるが、いや、それができないから今困ってるんだけどという話だ。無理に今ここを意識してみるのは、離人感のもどかしさを余計感じて落ち込んでしまう。私的には、今ここを意識するのは”結果的にできるようになること”だと思っている。
自己注視と反芻思考は自分を辛いことから守る防衛の役割を担ってきたが、私はその監視と緊張の世界から戻れなくなっているんじゃないかと思う。
私が考えを止められない理由
- 社会的孤立への恐怖
発達障害のせいか、空気が読めないふるまいをして孤立してきたので、「ちゃんと考えてないと変な事を言ってしまう」と恐れてきたから。 - 私を傷つけた人たちへの拒絶
「私をいじめた人たちや親みたいに、短絡的に行動してしまうやつになりたくない」「私はあんなバカじゃない」と思って生きていたから。そのため、「浮かんだ感情は必ず自分の頭の中で分析し、言語化しないといけない」という独特な観念に囚われており、頭が休まらない。 - 死への恐怖
突然死が怖くて常に体の様子を見張ってないといけないと思っている。また、「緊張(≒解離)をやめてしまうと、今考えてるこの私の意識が消えて別の人に変わってしまうのでは」と考えているから。
人間関係の希薄さが解離を加速させてる?
異常な緊張とコミュニケーションの下手さで、人間関係をどんどん失ってここまできた。しかし、現実感がなくグラグラしている中、一人で過ごす時間が多すぎると解離にかなり悪影響だと感じる。人と存在が違うという感触がないと、自分が一体誰なのかますますわからなくなるからだ。
やはりある程度は日頃から人との交流があったほうがいいと思っている。今からそれを作っていくのはとても難しいが。
インターネットの影響も?
メンタル不調になりはじめた中学生のとき、ネットをすると離人感が出ていた。ネットが「ここにいない」を促進するかもしれない。しかし、もうこんなスマホが手放せない時代だ。私は不安と孤独感がすごいから、ネットにのめり込む。やめたくてもやめられないが、特定の時間帯でデジタルデトックスを心がけるようにしている。
6. 離人症への対処
薬とカウンセリング
今のところ、離人症の薬というのは聞いたことがない。ただ、離人症以外の症状を治療していたら離人症が治ったという人たちはいる。
私もいろんな薬を飲んだが、それで離人症が良くなったことはない。ADHD治療薬とフラッシュバック対策の漢方(神田橋処方)は飲んでいるが、その2つで「頭の整理」「興味・関心の回復」ができてきたことで、離人症への理解が深まったり、体の力を抜くのがやや上手くなったりはした。
カウンセリングではトラウマなどについての知識を得ることができた。また、カウンセリングでEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)を受けたことにより、私にはEMDRが向いているとわかった。その理由として、トラウマを処理できているからというより、他のものに注意を逸らすことができているからではないかと考える。
私に向いていると思った対処法
離人症がすごく楽になるということもないが、少しは身体の力が抜けて楽になる方法はある。
・タッチセラピーやカイロプラクティック
タッチセラピーは、身体に優しく手を当ててもらうことで、リラックス効果や精神的な安定をもたらす療法だ。種類や名称はいろいろあると思うが、心理士がやるやつから、民間のスピリチュアルっぽい人がやるものまである。
やってもらうと、少し脱力できたり、息がいつもより深く吸えたりする。多分、安心しているのだ。私はこういう外的な要素でケアしてもらうほうが向いていると思う。自分のことを自分と思えないのに、自分が自分に対してケアとか、難易度高すぎる。
同様に、カイロプラクティックも向いているな~と思っている。普段、美容室のシャンプーやマッサージとか行ってもガチガチ緊張しててくつろげないのに、タッチやカイロは不思議と眠くなれる。
タッチもカイロも一回(約一時間?)に5千円~くらい払う必要があるのがネックである。
・遠くの音を聞く、遠くを意識する
注意訓練法というものの一環と思うが、遠くの音に耳を澄ませようとすると、なんだか体がちょっと楽になったりするのである。同様に、自分がすごく遠~くの場所(離島や別の惑星とか)とかにいるイメージをすると、ほっと息をつけるときがある。
これはおそらく、過度な自己注目から解放されているためである。過去のトラウマから、自分をいつも監視して緊張しているが、そのプレッシャーから解放されているのだ。この「遠く」シリーズをやりだしてから、身体が勝手にブルッと震えて緊張を逃す技ができるようになった。
・本音を話して泣くこと
私は病院やカウンセリングでも毎回すごく緊張しているので好きに喋れない。でも、過去のことや今の辛いことを話していて泣いてしまうことはごくたまにある。そのときに体の重みを感じてちょっと楽になるのだ。これは、泣くことにより副交感神経が優位になるからだと思う。
・トラウマや解離性障害について知ること
多分、これがないと私は自分のことを整理することができず、今頃もっと、得体の知れない症状や恐怖に困っていたと思う。どうしてこんな困り事があるのかというのを説明できると、安心感が違う。
そして私には「ポリヴェーガル理論」という考え方が向いていると思っている。ポリヴェーガル理論は、人の心と体がどうやって安心を感じたり、危険に反応したりするのかを神経レベルで説明する理論だ。一般の人でも読めるやさしい解説本もある。
学習のためにおススメの本を紹介します。
・『解離性障害のことがよくわかる本』
・『トラウマのことがわかる本』
・『不安・イライラがスッと消え去る「安心のタネ」の育て方』
・『今すぐできる心の守りかた』
7. 離人症回復へ必要なこと
あくまで私の離人感についての話だが、回復に必要なのは「安心感」だと思っている。
これまで数度、数分間レベルで、現実感が戻ったときがあった。恋愛で舞い上がっていたときか、一分一秒の時間に追われていて他のことが考えられなくなっていたときだ(具体的には飛行機の時間を気にしていたとき)。
恋愛は「存在を求められている」と自己肯定感が上がるし、時間に追われていたら自己注目から注意が逸れる。私はいつも自分を責めすぎて緊張しすぎているのだ。
恋愛は簡単に今日からひとりで始めようみたいなことはできないし、必要も強制力もないのに時間に追われてみるというのは難しい(そんな元気もやる気もない)。
他の、現実感が少し薄れる時々のことも考えると、つまりは「安心感」が鍵なんじゃないだろうか。自分を責めなくてもいい、緊張して常に頭をグルグル動かし警戒してなくてもいい。そんな時間を過ごせること。
家でひとりでもできるリラックス方法とか安心感を得る技術みたいな指南は世の中に溢れているが、ここまで解離してると難易度高いと思う。私は、外的要因によるドデカ安心に溶かされたいのだ。それもどうやるの?ってお話ですが。
以上が、私の離人症経歴となります。
離人症についてもっと知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。